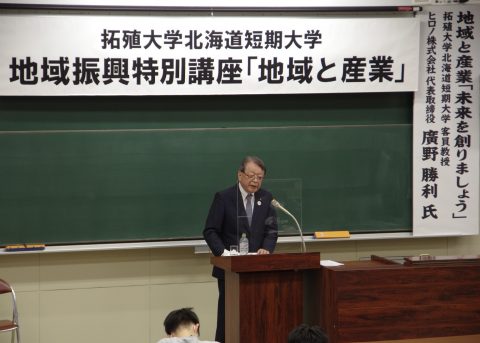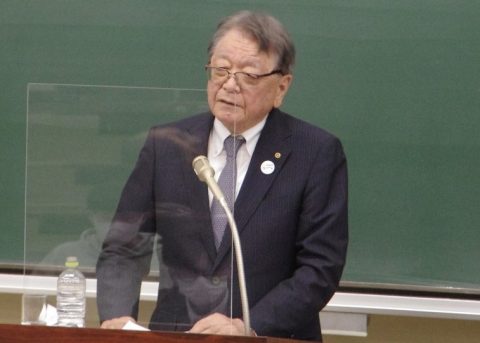10月23日(土)16時より、第25回保育セミナーが開催されました。昨年度は新型コロナ感染拡大により実施できませんでしたが、本年度は本学絵画工作室の会場から参加者をオンラインで結び、60名(オンライン56名、本学会場の深川市内の保育者様4名)のご参加がありました。
本セミナーはリカレント教育として、創意工夫を活かした創作や、幼児教育の最新動向について参加者と共に考えること、および、本学科のOG・OBを核として、地域の保育の質を向上させる保育者間の学びのネットワークを構築することを目的としております。
講座1では本学非常勤講師の大和正枝先生より、「折り紙で作ったものを壁飾りに」というタイトルでワークショップが行われました。折り紙でハロウィーンのかぼちゃや黒猫、おばけを折り、同じく折り紙で作ったフレームに貼り付けて、かわいらしい壁飾りができました。年齢による展開例や、クリスマスや母の日の壁飾りへの応用も紹介されました。
講座2では本学の萬司教授より、5歳児の教育プログラムの議論を皮切りに、小学校学習指導要領との連携の視点から講義が行われました。幼稚園教育要領など保育3法令で、保育者は多様な役割を果たしながら、幼児の自発的な遊びを通して、一人一人の資質・能力を育んでいくことが求められていることを確認しつつ、しかし、小学校の学習の前倒しではないことが念押されました。
講座後の交流会では、ご参加の先生から、子どもの主体を活かすための現場での悩みが話され、短い時間でしたが、有意義な時間を共有することができました。
終了後のアンケートでは「折り紙のバリエーションが広った」「子どものために何ができるか考えながら計画を立てたい」など、セミナーを経て日々の振り返りと今後につなげる回答が寄せられました。
ご多忙の中、ご参加くださり、誠にありがとうございました。 近い将来、皆様と実際に顔を合わせながら保育セミナーが行えることを願っております。