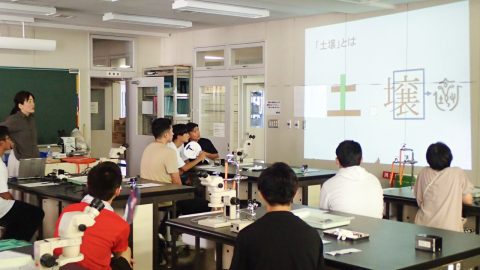1件目は雨竜町の水稲農家永野農場を訪問しました。ご夫婦とも本学環境農学科の社会人卒業生で、現在は雨竜町に新規就農して水稲20haとヒマワリを栽培しています。関東でサラリーマンをしていた永野義典さんは、農業の魅力にきづき北海道で農業を志したということでした。土地利用型農業は自然を相手に体と頭を動かして働くところがおもしろいと感じており、農家後継者の学生たちには新鮮な視点でした。就農する前に必要なことは何ですかという学生の質問に対して、農業の知識に加え同じくらいコミュニケーション能力が重要だと教えていただきました。
つぎに妹背牛町水稲直播研究会を訪問し、会長の長谷浩幸さん(拓殖短大卒業生)と顧問の熊谷勝さんからお話をお聞きすることができました。研究会は平成5年に当時はマイナーであった直播栽培の技術向上を目指し地元の水稲農家が中心となって立ち上げたものです。お二人からは近年はスマート技術が普及しているが、水田の稲をみることは農家の基本であること、そして周囲のいろいろな人を農業にとりこむこともこれからは大切になってくることをお話しいただきました。
農作業のお忙しい時期に貴重なお話をしていただき視察にご協力いただいたみなさまに深謝申し上げます。





●公式Instagram:takushoku.hc.ac.jp

●公式Twitter:@Takushoku_hc

















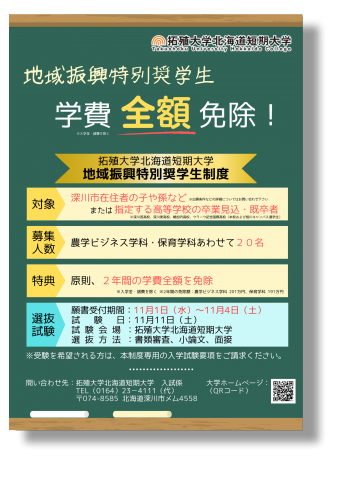






![公開講座ご案内チラシ[PDF]](https://www.takushoku-hc.ac.jp/tak/wp-content/uploads/2023/09/R05_takushoku_sake-339x480.jpg)
![FAX申込用紙[PDF]](https://www.takushoku-hc.ac.jp/tak/wp-content/uploads/2023/09/R05_takushoku_sake_FAX-339x480.jpg)