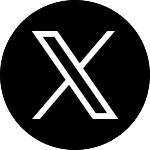保育学科閉科メモリアル事業「歴史と未来をつむぐ一日」第1部「第29回保育セミナー」が開催されました。(10月18日)
10月18日(土)13時30分より、保育学科最後となる「第29回保育セミナー」が行われ、一般参加者52名(内、オンライン10名)と保育学科の学生26名全員との合計88名の参加によってスノークリスタルホールが一杯になりました。
今回は、「『遊び』と『自然』が育む子どもの主体性と豊かな心―AI共存社会を見据えた幼児期の土台作り」をテーマに、拓殖大学北海道短期大学保育学科閉科記念事業「歴史と未来をつむぐ一日」の「第1部リカレントプログラム第29回保育セミナー」として開催されました。
保育学科の学生は前日の会場設営から関わり、セミナー当日にはそれぞれの講演後に質問するなど積極的に参加する姿が見られました。
当日は、玉木保育学科長の挨拶のあと、基調講演として、文教大学(埼玉県)の及川智博先生による「子どもと大人が共主体であるための『構え』」が行われました。及川先生からの質問に挙手をしたり口頭で回答したりするなど緊張する場面が幾つもありましたが、それによってひとつずつ考察を深めながら“遊び”について専門的に理解することができました。
それに続く実践者トーク①では「子どもの主体性を育む環境とは何か?~遊び、自然、AIと共存する社会を生き抜く力」について、森のようちえん全国ネットワーク連盟初代理事長(長野県)・飯綱高原ネイチャーセンター&冒険遊びの森代表の内田幸一先生から、実践者トーク②では「自然の中で育むかぜっこのインクルーシブ保育」について、たどし認定こども園(深川市)園長の殿平真先生から、子どもたちの生き生きとした映像や画像の紹介を交えてのご講演を賜りました。
“遊び”について考え、その実践を見せていただくことによって、幼児期における「遊び」と「自然」を通じた非認知能力の育成の重要性を多角的に考え、AIと共存する未来社会を見据えた保育のあり方と保育者の役割を展望することができました。
そしてセミナーの最後には、本学の教員として長く保育セミナーに携わってこられた山田克已先生から、この第29回保育セミナーのために作曲してくださった新しい歌「Happy Day〜拓殖大学北海道短期大学保育学科閉科SONG〜」のプレゼントを頂いて、セミナーが終了しました。
本セミナーにご協力、ご参加を賜りました皆様、そしてこれまで応援し支えてくださった皆様に、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

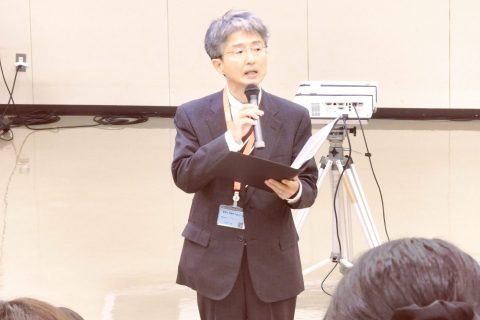













●公式Instagram: takushoku.hc.ac.jp

●公式X(旧Twitter): @Takushoku_hc