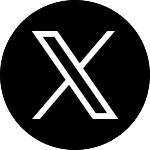北海道ラッカセイサミット情報交換会を開催しました。(2月12日)
2025年2月12日、拓殖大学北海道短期大学にて「北海道ラッカセイサミット2024年度情報交換会」が開催されました。本サミットは、2016年度から北海道における落花生栽培の情報交換を目的に、夏は現地見学、冬は情報交換会として定期的に実施されています。今回は、対面参加40名、Zoomによるオンライン参加50名の計90名が参加しました。
会の冒頭では、主催者である拓殖大学北海道短期大学の学長が挨拶を行い、その後、基調講演や情報交換会が行われました。
1つ目の基調講演では、酪農学園大学准教授・岡本吉弘氏が「北海道品種の作出を目指して―どの育種法でアプローチするか―」と題し、北海道に適した品種育種について講演されました。
2つ目の基調講演では、千葉県農林総合研究センターの津金胤昭氏・鈴木健司氏が「千葉県のラッカセイ栽培の情況」と題し、ラッカセイ栽培の本場である千葉県における現状や機械化について講演されました。


その後の情報提供では、以下の報告が行われました。
• 「私の札幌でのラッカセイ栽培」(札幌市いきいきファーム・吉岡宏直氏)
• 「十勝地域におけるラッカセイ栽培の実際と栽培法による比較」(十勝農業試験場・田澤暁子氏)
• 「ラッカセイの収穫時期が子実に与える影響」(大道技術士事務所・大道雅之氏)
• 「ラッカセイ乾燥方法の検討」(拓殖大学北海道短期大学2年生・吉田央祐さん)




休憩後の情報交換会では、以下のテーマについて活発な議論が交わされました。
• 「国産ラッカセイ収穫機の開発について」((株)エース・システム代表・菅原康輝氏)
• 「北海道内のラッカセイの現状と今後」((株)TOMTEN 柴田真樹氏、メムロピーナッツ 藤井信二氏、公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター地域クラスター創造支援部 對馬貴子氏)


これまでの取り組みや今後の課題について議論が交わされ、地域活性化に向けた具体的なアプローチも共有されました。時間が足りなくなるほど熱のこもった意見交換が行われ、充実した会となりました。
本サミットを通じて、北海道内外の関係者が一堂に会し、落花生栽培の現状や課題、そして今後の展望について活発な意見交換が行われました。拓殖大学北海道短期大学では、今後もこのような情報交換の場を提供し、地域農業の発展に寄与していく予定です。
●公式Instagram: takushoku.hc.ac.jp

●公式X(旧Twitter): @Takushoku_hc